ハクビシンは雑食性の動物で、特に野菜や果物が大好物です。
もしも、家庭菜園が食い荒らされているなら、ハクビシンの餌場になっているかもしれません。
この記事ではハクビシンの歯型や特徴・食べ跡から、他の動物と見分ける方法について紹介します。
さらに、ハクビシンによる被害を防ぐ方法についても解説します。
ハクビシンの食べ跡を調査
ハクビシンの食害にあった野菜や果物には特徴的な跡が残ります。
ハクビシンの食べ跡の特徴や歯型の特徴を具体例で確認してみましょう。
ハクビシンによる食べ跡の特徴
1.とうもろこし

- 特徴
ハクビシンはとうもろこしの茎を倒して実をかみ取るようにして食べるため、茎が斜めの状態で残ります。
2. みかん

- 特徴
木の上から頭を下にして果頂部からかじり、基部を残すのがハクビシンの特徴です。
また、実を1度口の中に入れてから皮を下に吐き出します。
3. ぶどう

- 特徴
ぶどうの袋を口で下に引き裂いて、その穴から顔を突っ込んで実を食べます。
4. すいか

- 特徴
すいかの中身を手で取ることができず、開けた穴に顔を入れて食べるため、大きな穴が開いています。
ハクビシンによるきゅうりの食べ跡

ハクビシンは鋭い歯できゅうりの皮をかみ切るため、かみ跡が残るのが特徴です。
また、きゅうりの一部をかじって食べるため、食べ残しが見られることがあります。
ハクビシンの歯型の特徴
ハクビシンの歯型は鋭く刺したような食べ跡が多く残されます。
これは、果物や野菜を食べる際に突き刺すようにして食べるためです。
また、1〜2本の短い歯型が不規則に残され、果物にはV字の跡が残されるため、他の動物と見分ける際のポイントになります。
動物がかじった野菜の特徴は?
1.とうもろこし

- 特徴
アライグマは手先が器用なため、穂を持ってきれいに食べます。
茎が倒れることが多く、実を持っていくことも。

- 特徴
タヌキは食べ散らかす習性があり、茎が倒れたり泥が付着したりすることが特徴です。
実を持っていくこともあります。
2.すいか

- 特徴
アライグマは食べるために前肢を使って直径5〜6cmの穴を開けます。
くり抜くように実を食べるので、爪の痕がつくことがあります。

- 特徴
タヌキは他の動物が開けた穴を利用して口を使って食べます。
食べ散らかすのは、タヌキの食べた後の特徴のひとつです。
ハクビシンと他の動物との食べ跡を見分ける方法は?
動物にはそれぞれ特有の食べ方や、口の形状によってできる食べ跡、食べた後の散らかし方に違いがあります。
以下の表を参考に、ハクビシンと他の動物との食べ跡の違いを見分けましょう。
| 動物 | 食べ方の特徴 |
| ハクビシン | 果実が枝についたまま果頂部から食べ始め、皮を下に吐き出す 果実の皮にV字の跡が残るのが特徴 |
| アライグマ | 果物の皮をむいて食べることが多く食べた後は整然としている |
| タヌキ | 残骸が周囲に散らばるなど、食べ散らかすことが多い |
ハクビシンは殺してはいけない?
ハクビシンは「鳥獣保護管理法」によって保護されている動物です。
無許可で捕獲や殺処分すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
自宅の敷地内で小型の箱わなを使った捕獲に免許は必要ありませんが、一般的にわな猟免許が必要です。
また、捕獲には都道府県知事に駆除申請や、捕獲後の処理についての届け出を自治体に出す必要があります。
害があるからといって、勝手に捕獲・殺処分することはできません。
ハクビシンによる被害を防ぐためには?
ハクビシンは頭が入る隙間があれば自由に通り抜け、木があれば鋭い爪でスルスルと登ります。
ハクビシンによる被害を防ぐには、以下の対策が効果的です。
- 侵入口になる隙間をふさぐ
- 敷地を囲うなどして侵入口になりそうな隙間を頑丈なものでふさぎましょう。
- 餌になるものを片付ける
- 敷地内の果実は早めに収穫するか、網をかけましょう。
- ハクビシンが嫌がる臭いを発生させる
- ハクビシンが嫌がるニンニク・石油・木酢液などのニオイの強いものや、唐辛子などの刺激のあるニオイのものを置きましょう。
- ハクビシンが嫌がる音を発生させる
- ハクビシンは聴覚が発達しているため、大きな音や超音波を嫌います。
- 庭木の刈り込みをする
- 庭木の枝を伝って敷地内に侵入されないよう、枝を定期的に切りましょう。
- 有刺鉄線や融資鉄板
- 有刺鉄線や有刺鉄板を木や壁の上などに設置して登れないようにしましょう。
- 電気柵を設置する
- 電気柵を設置することで、物理的にハクビシンの侵入を防ぎます。
「ハクビシン 食べ跡」を調べている人がよく思う質問
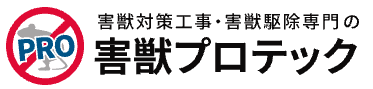


\ 関東・関西・東海・九州エリア対応! /
最短即日10分で現地に駆けつけ!
ご相談、現地調査&お見積り、出張費用すべて0円です。
まとめ:ハクビシンの被害にあわないように対策を!
動物の食べ跡や食べた後の散らかし方などを参考に、ハクビシンかどうかを確認できたら早急に対策しましょう。
ただし、ハクビシンは鳥獣保護管理法によって保護された動物のため、個人では積極的な対策が難しい場合があります。
対策しても効果を感じられない、対策が難しいといったときには、害獣駆除専門業者に相談することも視野に入れて検討してみてください。
害獣の被害から菜園を守るには早めに対策することが肝心です。
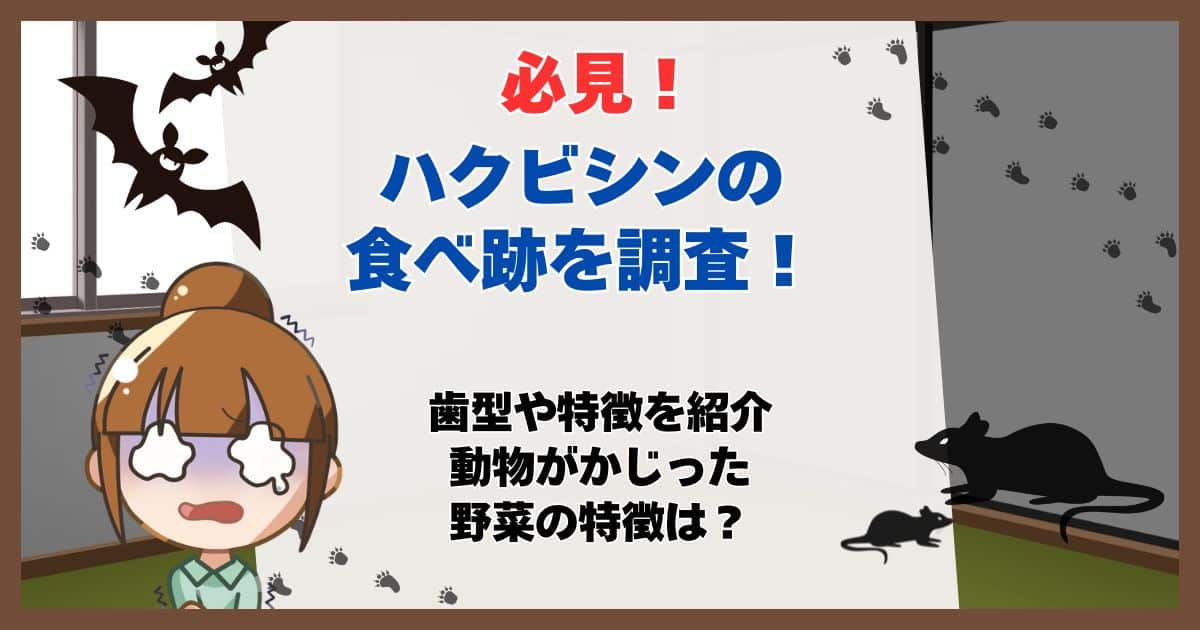





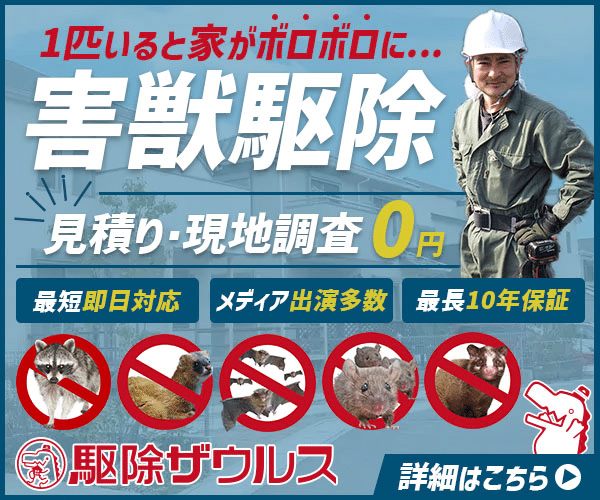





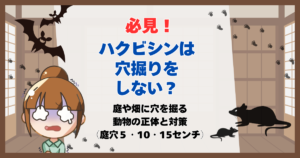
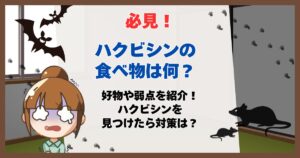
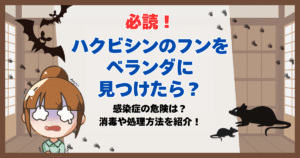
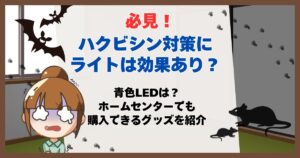


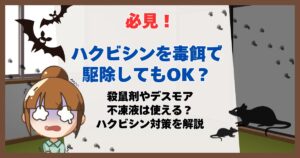
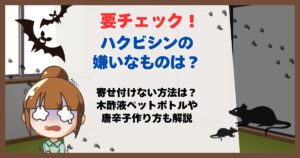
コメント