アナグマを見たことがある、という方は実は結構多くいらっしゃいます。
でも、アナグマの生態やなぜ害獣に指定されているのか知らない方も多くいる一方で、そんな害獣のフンによる被害も増えています。
この記事では、アナグマやクマ、タヌキ、イノシシ、ハクビシンといった害獣指定された動物のフンの見分け方を紹介します。
もし、庭や家庭菜園に紹介したようなフンを見かけた場合、フンをした犯人が頻繁に出入りしている可能性があるかもしれませんので、参考にしてみてください。
アナグマのふんを写真で解説

アナグマのフンの特徴として「地面を少し掘ってある」「同じ場所で何度もフンをする」ことが挙げられます。
地面を少し掘る場合、深さはその時々で違い数㎝の時もあれば20㎝ほど深く掘る場合もあります。
同じ場所で何度もフンをするのは「溜めフン」という習性を持つためになり、この溜めフンによって強烈な異臭や沢山の害虫を引き寄せてしまう原因になっています。
庭の動物のふんの見分け方

この項では、庭や畑などに残されたフンの特徴からどんな動物のフンなのか、見分け方を紹介します。
| 画像 | 動物名 | 特徴 |
|---|---|---|
 引用元:学校法人玉川学園 | アナグマ | ・かなり強い悪臭 ・泥が混じっている ・直前に食べたものが完全に消化されずにフンに混じっている ・数㎝~20㎝程度の穴を掘り、そこにフンをする習性を持つ ・溜めフンの習性を持つため、同じ場所に何度もフンをする |
 引用元:YAMAP MAGAZINE | クマ | ・他の動物に比べ、体格通りの大きいフン ・直前に食べた物によってフンの色やニオイ、形状が変わる ・通常(木の実などを食べたあと)のフンはほぼ無臭 ・フンの鮮度でクマが近くにいるのか判別できる |
 引用元:YAMAP MAGAZINE | タヌキ | ・溜めフンをする習性を持つため、山盛りのフンが出来ている ・かなり強い悪臭 ・果物の種子が混じっていることがある ・黒く丸いフンが集まったような形 |
 引用元:Honda Woods | イノシシ | ・成獣の場合、かなり大きい ・小さい塊がいくつもくっついたような形 ・木の実の種や殻、昆虫の死骸が目立つ |
 引用元:くらしのマーケット | ハクビシン | ・果物の種子やトウモロコシなどの野菜が混じっていることが多い ・他の動物と比べると臭くは無い ・溜めフンをする習性を持つため、同じ場所に何度もフンをする |
熊のフンの見分け方

クマのフンは通常の動物とは違い大きなフンをします。
また、排泄する直前まで食べていたものによって色やニオイ、形状が変わるため分かりやすいのが特徴です。
例えば、木の実などを食べたクマのフンはほとんど臭くありませんが、リンゴなどを食べたクマのフンはリンゴのニオイがしますし、葉っぱなどを食べた場合は緑色のフンをします。
ほかにも、クマのフンは危険を知らせる証拠になり、フンの鮮度によってクマがどのくらい前までその場に居たのかを知る目安となります。
そのため、森などをハイキングする際のフィールドサインとして用いることもあります。
アナグマの生態

この項では、アナグマの生態について紹介します。
アナグマの特徴
アナグマ(ニホンアナグマ)は夜行性で、昼間は巣穴で休息しています。
温厚な性格で、体格もずんぐりとしているためか、素早く動くことは苦手です。
警戒心は低いようで、人が近づいても逃げないこともあり、エサ探しや住処探しに夢中になっていると人が近くに居ることも気づかないほどです。
体の大きさや色のためか、タヌキやアライグマ、ハクビシンとよく間違われています。
名前の通り、穴を掘ることが大得意で過去には1㎞に及ぶ巣穴が見つかった事例もあります。
前足には鋭く長い爪があり、その爪を使って穴を掘り進めます。
アナグマの食べ物
食性は雑食となり、昆虫やミミズ、カエルやモグラといった小型の動物を好んで捕食します。
ただ、果物や野菜なども食べることも多く、トウモロコシやイチゴ、スイカを栽培している農家の方は食害に頭を痛めています。
また、根っこから掘り起こされることで作物がダメになるなどの被害も報告されています。
アナグマの巣穴
大きな岩の下や柔らかい土があるところを巣穴に選ぶことが多いようです。
アナグマの巣穴は親子で受け継がれていくため、家族が増えれば増えるほど巣穴はどんどん深く、部屋数も増えていきます。
巣穴への出入口は何か所も存在し、過去には1㎞に及ぶ長さと部屋数が50もある巣穴が報告されています。
アナグマの生息範囲
アナグマ(ニホンアナグマ)は日本固有の種となっており、沖縄や北海道を除く日本全国に生息しています。
特に、九州や中国地方では報告例が多く、東北地方や中部地方になると報告例が少なる傾向にあります。
アナグマによる被害

アナグマによる被害は大きく3つ挙げられます。
- 畑や家庭菜園へ侵入することで起こる農作物への被害
- 溜めフンによるニオイ、害虫被害や感染症のリスク
- 巣穴を掘ることでできる穴による建物などの倒壊の恐れ
アナグマはカエルやネズミ、ミミズなどの小動物や昆虫を主に食べますが、果物や野菜も食べます。
そのため、畑や家庭菜園に侵入し大切に育てている果物や野菜を食い荒らしたり、根本から掘り起こしてしまうことで農作物をダメにしてしまうこともあります。
アナグマには同じ場所でフン尿をする「溜めフン」という習性を持っており、ニオイによる被害のほか、そのフンによって害虫が発生することで精神的にも大きなストレスを感じることもあります。
そして、アナグマのフン尿で最も注意したいのは「感染症」の原因となる病原菌の存在です。
サルモネラ菌、トキソプラズマ、エキノコックスなど小さい子供やお年寄りなど、免疫力が低い方が罹患すると命に関わる感染症もあるため、注意が必要です。
アナグマは穴を掘り、巣穴を作ることを得意としています。
建物などの近くで巣穴となる穴を掘られてしまい、気づかないまま放置してしまうと、地盤が脆くなり建物が倒壊する可能性もあります。
そのため、アナグマを見かけた際には建物の脇や畑などに巣穴を作られていないか、注意深く見回りすることが重要となります。
アナグマのフンの処理方法は?

アナグマのフンを処理するにあたり、準備する道具がいくつかあります。
- 使い捨てのゴム手袋
- 使い捨ての不織布マスク
- ゴーグルやメガネ
- 長袖長ズボン
- ホウキとチリトリ
- 燃えるゴミ用の袋
- 除菌スプレーまたはアルコール消毒(70度以上)
フンが乾燥して空気中を舞っている可能性もあるため、必ずマスクとゴーグルやメガネをつけて吸い込んだりしないよう注意してください。
アナグマのフンをホウキとチリトリで手早くゴミ袋にいれたらしっかりと縛り、除菌スプレーでしっかりと除菌してください。
もしも室内での処理となった場合は、除菌スプレーを万遍なく散布し、使い捨ての雑巾などでしっかりと拭きとってください。
アナグマ対策で注意するべきこと
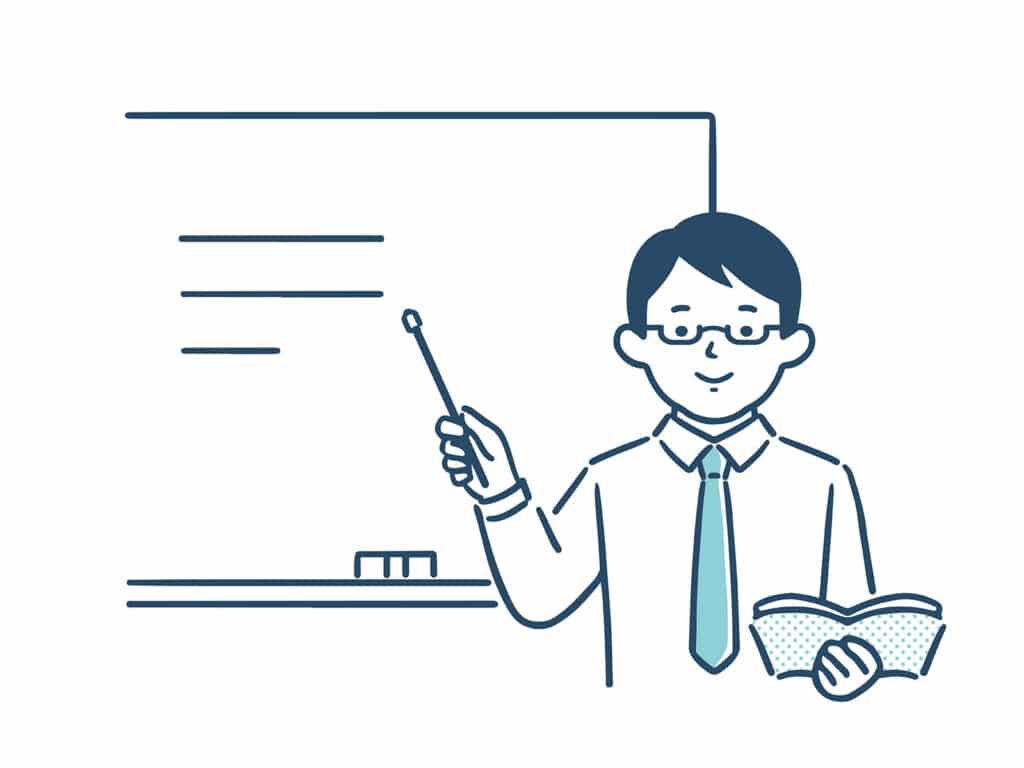
アナグマは「鳥獣保護管理法」という法律により守られた動物です。
そのため、許可無く捕獲や殺傷してしまうと「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に科されることもあるため、侵入対策や追い払う際には注意してください。
「アナグマ ふん 写真」を調べている人がよく思う質問
まとめ:アナグマのフンを見つけたらすぐに対策を!
この記事では、アナグマのフンを写真で解説したり、熊・たぬき・イノシシ・ハクビシンなど動物のふんの見分け方を紹介しました。
アナグマは体格がずんぐりしていて、温厚な性格のためか警戒心が低い動物です。
そのため、気づかずに近づいてしまい驚いて攻撃されてしまうなどの被害報告もあります。
また、アナグマは同じ場所でフンをする習性(溜めフン)を持つため、一度フンを見つけた場所は何度も訪れる可能性がかなり高いため、忌避剤やハッカなどのアナグマの嫌いなニオイを散布しておくなどの対策をする、除菌スプレーなどを使ってしっかりと除菌しておくことが重要です。
いつの間にか大きな巣穴を作られてしまった、大量のフンをされてしまって困っているが、自身だけでは対処が難しいと感じる方は、害獣駆除の専門業者へ相談することをおすすめします。
たくさんの経験と知識、道具を使って追い出し~清掃・除菌、再侵入対策までをしっかり施工、サポートしてくれます。
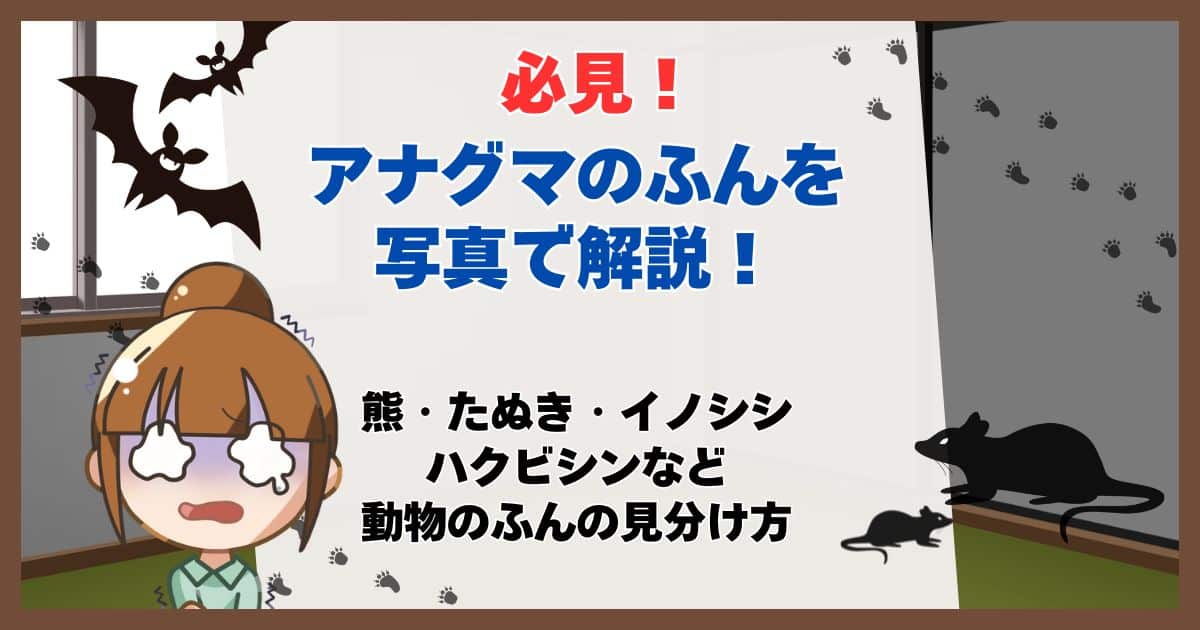
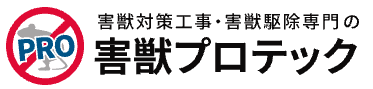


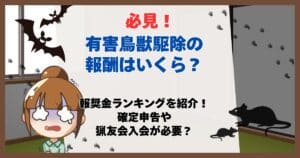
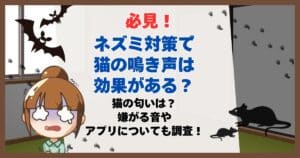
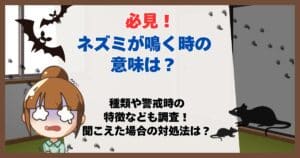
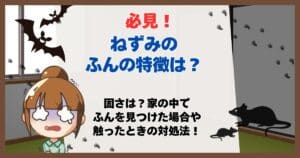
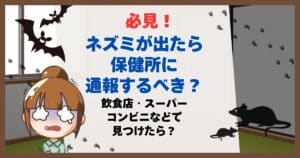
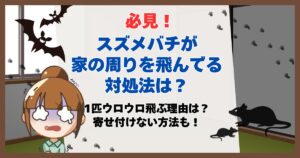
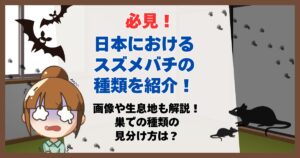
コメント