ハクビシンによる農作物への被害が出たという話を聞くことはありませんか。
穴掘りの形跡まであって、早めの対策をしないとほかのところにまで被害が出てしまいます。
でも、ちょっとまってください。
その被害は、本当にハクビシンだけのものでしょうか?
似たような動物達がいるのでよく勘違いされることもあり、対策を間違えると何度も同じ被害に合ってしまいます。
そこでこの記事では、ハクビシンは穴掘りをするのかについてのほか、穴を掘る動物の正体についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ハクビシンは穴掘りしない?庭の穴を掘る動物の正体は?

実は、ハクビシンは穴掘りが苦手です。
穴掘りよりも木登りが得意で、主に木の上で生活をしています。
そんな勘違いで疑われているかわいそうなハクビシンに変わって、穴掘名人な動物達をご紹介します。
ハクビシンは実は穴堀が苦手!
まず、ハクビシンは穴掘りが苦手です。
穴掘りよりも木登りを得意とし、木の上が主な生活場所となっています。
長い尻尾を使ってバランスを取ることで電線の上を渡るなど大道芸のようなことも可能です。
庭穴の正体①イタチ

穴掘り名人の正体1「イタチ」です。
イタチは気温変化の少ない土の中を好み、地中にいるミミズなどを穴掘りして食べています。
人が一度耕した畑はイタチにとって簡単に掘ることができるため、食料を探すためや巣穴としてあちこち掘り返されてしまいます。
イタチの作る穴の入り口の大きさは最大でも3㎝~5㎝ほど、穴の中は複雑に入り組んでいる事も多く、住処以外にも餌となる獲物を捕らえるのにも使用しています。
庭や畑で巣穴を作られてしまうと、農作物への被害だけでなくふん尿による悪臭被害も起こる可能性が高くなってしまいます。
庭穴の正体②ネズミ

穴掘り名人の正体2「ネズミ」です。
ネズミは庭などに穴を掘って、そこに段ボールや木の葉といったものを持ち込こむことで住処を作っています。
ネズミの体は小さいので掘る穴も比較的浅いのが特徴ですが、中は入り組んでおり外敵から逃げるための工夫がされています。
また、土に穴を掘るネズミは「ドブネズミ」「ハツカネズミ」の2種類です。
庭穴の正体③タヌキ

穴掘り名人の正体3「タヌキ」です。
タヌキは穴掘りが得意で、住処のために必死に穴掘りをします。
また、地中にいる昆虫やミミズを探し出すための穴も掘ります。
庭や畑に作る穴の大きさは7㎝~10㎝ほどでタヌキの体が入る大きさになり、もしタヌキの作ったであろう穴を見つけた場合、穴を空けた本人が近くにいる可能性はかなり高いです。
余談ですが、タヌキはよく「アライグマ」と間違われることが多いのですが、実はアライグマは穴掘りが苦手です。
見分けるためのポイントは「尻尾のしましま」で、しましまがあるのは「アライグマ」無いのが「タヌキ」になります。
タヌキとアライグマを見分ける際の参考にしてみてください。
庭穴の正体④アナグマ

穴掘り名人の正体4「アナグマ」です。
アナグマは名前の通り穴を掘るのが得意な動物で、地中にいる昆虫やミミズのほか、カエルやモグラを掘って食べており、農作物や果実も掘り起こして食べてしまいます。
アナグマの作る穴の入り口は25㎝以上になることもあり、穴の長さは最大で50mもあるといった事例も存在します。
近年、アナグマは人里で見かけることが多くなってきており、合わせて農作物への被害が増えていることで問題となっています。
特に農作物を食い荒らすだけでなく畑を掘り起こされてしまい、農作物がダメになってしまうことで農家の方も頭を悩ませています。
庭穴被害を放置するとどうなる?
庭や畑への穴を放置すると大事に育てている農作物などへの被害がでるほか、穴を掘る動物の中には獰猛な性格のものもいるため、思わぬケガをするなどの人的被害にもつながりかねません。
この項では、庭などに作られた穴を放置するとどんな被害につながるのかご紹介します。
農作物を育てている場合は食害にあいやすい
庭や畑に穴を掘られる被害として一番に挙げられるのは農作物への被害です。
想像されているよりも深い穴を掘る動物もいるため、根までおられてしまい枯れてしまうという被害も発生しています。
また穴被害だけに止まらず、もう少しで食べ頃というタイミングで農作物を食い荒らされてしまう被害も増えてきています。
家屋へのダメージ
穴を掘る害獣の中には、深い穴を掘ることでそこを住処とするものもいます。
もし、そんな住処を建物(倉庫など)の下に作られてしまうと地盤が脆くなり、最悪の場合その建物が倒壊する可能性もあります。
特に日本は地震の多い国なので、地盤がしっかりしているかどうかで被害の大きさが変わってきます。
健康被害につながる恐れも
掘られた穴の中や近くには掘った本人達(害獣)のフンや尿のほか、ノミやダニといった寄生虫がいる可能性がかなり高いです。
特にフンや尿には様々な病原菌が潜んでおり、中には健康な人でも一度感染してしまうと命に係わる感染症も存在するので絶対に素手で触れないようにしましょう。
以下に病原菌のほんの一部をご紹介します。
食中毒を引き起こす病原菌で知られており、発症すると腹痛に始まり下痢や嘔吐、発熱、脱水などの症状が現れます。
小さい子供や高齢者のような免疫力が低い方が発症すると、他の臓器に対しても大きな負担がかかることで重症化する可能性もあります。
フンを媒介して感染する感染症で、軽症の場合はインフルエンザのような症状で終わりますが、重症化するとワイル病へと発展してしまい、黄疸や鼻血を伴った出血のほか皮膚や肺、消化管からの出血が起こるなどの症状がでてきます。
また、重症化の中でも腎不全になってしまう可能性もあり、その場合は透析治療が必要になることもあります。
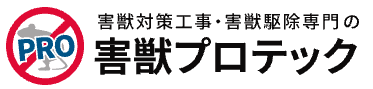


\ 関東・関西・東海・九州エリア対応! /
最短即日10分で現地に駆けつけ!
ご相談、現地調査&お見積り、出張費用すべて0円です。
庭穴を掘る害獣の対策法は?
庭や畑に穴を掘る害獣を放置していると、被害はどんどん大きくなっていきます。
害獣の種類によっては、被害は建物の中へ侵入される事態にまで発展することで屋根裏や壁の中、床下を住処にしてしまうものまで出てきます。
そのため、早期に対策を行うことが被害を最小に抑えることにもつながります。
ただし、イエネズミと呼ばれる(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)以外の害獣は、鳥獣保護管理法や外来生物法と呼ばれる法律の対象となっているので、許可の無い捕獲や殺傷は禁止されています。
ここでは、害獣達をむやみに殺傷しない方法の対策をご紹介していますので、参考にしてみてください。
生態系および、人の生命や体や農林水産業へ問題を引き起こすまたは、問題を及ぼすおそれのある外来生物を特定外来生物と指定し(飼育、栽培、保管、運搬、輸入、放出、譲渡)を規制。
引用元:自然環境局 日本の外来種対策
市販の忌避剤を使用する
本来はどの害獣による穴なのかを特定することが大事になってきます。
ただ、素人目では穴の大きさでしか判断は難しいでしょう。
そこで、市販されている忌避剤をおすすめします。
市販されている忌避剤はタイプ別に種類があるので、場面に応じたものを使用するのがいいでしょう。
・スプレータイプ
害獣の嫌うニオイを噴射しニオイ成分を拡散することにより、害獣にとってストレスのかかる環境にします。
即効性はあるが、持続性は低く数十分のものもあれば数日しか効果が無いものが多いのが特徴です。
・固形タイプ
害獣の嫌うニオイ成分が含まれた固形物を設置することで、害獣を寄り付かせないようにします。
持続性は高く、1ヶ月~2ヶ月ほど効果が持続するものもあります。
・燻煙タイプ
煙により広範囲へ害獣の嫌うニオイ成分を拡散させることができ、即効性もあるほか効果も数日間持続するものも多いのが特徴です。
ただし、ペットなどを飼っている方はペットにストレスをかけてしまう恐れがあるため、使用時には十分な注意が必要になります。
どのタイプにも共通しているのは、外で使用する場合の持続性は天気に左右されてしまうという点です。
雨が降ってしまえば、忌避剤を使用してもニオイ成分が流れてしまう可能性もありますので注意が必要です。
超音波を流す
害獣のほとんどは夜行性のものが多く、音や光といったものにとても敏感なので大きな音や超音波などに対して強い嫌悪感を示します。
超音波は通常、人間には聞こえない高周波による音波となり、害獣の耳はそんな超音波を拾うことができます。
害獣にとってはその超音波はとてもストレスのかかる音に聞こえるのです。
ただし、害獣の中にはそんな音に慣れてしまう個体も出てきてしまうこともあるため、長期間の使用はあまりおすすめしません。
また、小さい子供の耳には「キーン」という音が聞こえることもあるので、使用する際は十分注意してください。
センサーライトを設置
害獣の中には夜行性のものが多く、強い光や音に対してとても敏感なので、突然強い光を当てられると恐怖感や不快感といったストレスを感じます。
さらに、強い光を常時点灯させることで夜でも明るい環境を作り出すと、害獣が住み着いてしまうことも防ぐことができるうえ、強い光を明滅させる(ストロボ発光)ことで、害獣に対し強い恐怖心を植え付けることも可能です。
センサーライトには電池式とソーラー式の2つの種類があり、電池式は定期的な電池交換を必要とします。
ソーラー式は電池式のように定期的な交換は必要ありませんが、ソーラーによる充電が行えない暗い場所への設置はできないので、状況によって使い分けることをおすすめします。
畑の場合は電気柵も効果的
電気柵は最も高い効果が期待できる方法です。
穴掘りが得意な害獣でも、鼻先に電気が流れれば驚いて逃げ出し、畑の周りに使用されている柵は危険であると認識すれば畑には寄り付かなくなり、再侵入の防止にも効果を発揮します。
ただし、注意点としてコストがかかること、柵の高さや設置場所の調整が難しいこと、定期的に除草しないと雑草がふれることで電圧が低くなり効果が薄まってしまうことです。
庭穴を掘る害獣の相談先はどこ?
庭などに穴を掘る害獣被害を受けたら次の2つが相談先になります。
・市役所、区役所、保健所といった公的機関
公的機関では害獣駆除といった作業は取り扱っていません。
ただ、捕獲機の貸し出しのほか、害獣駆除専門業者を紹介してもらえるといったサポートはしてもらえます。
気を付けたいのは、捕獲機を使用する場合、事前に「鳥獣の捕獲等許可申請書」などの公的書類を提出する必要があります。
これは、害獣と呼ばれていてもイエネズミ以外の動物は鳥獣保護管理法という法律で厳しく守られているためです。
また、公的機関で紹介された害獣駆除専門業者であっても、支払い金額やサービスの内容については自己責任となるため、紹介された専門業者を含め複数の業者に相談し見積りをとることをおすすめします。
・害獣駆除の専門業者
早期に事態を収拾したい、害獣と対面するのは怖いなどと考えている方は害獣駆除の専門業者へ相談することも方法の一つです。
また、専門業者なら確実に害獣の駆除とその後の対策やフォローなども行ってもらえるので安心感も得られます。
「ハクビシン 穴掘り」を調べている人がよく思う質問
まとめ
ハクビシンは穴掘りが得意ではありませんが、尻尾を器用に使い木登りや電線の上を伝って移動することができます。
もし、自宅の庭や畑に穴を見つけた時は、ハクビシン以外の害獣(アナグマ、イタチ、タヌキなど)を疑ってみてください。
鳥獣保護管理法により許可の無い捕獲や殺傷は禁止されていますが、市販されている忌避剤などを使用すればある程度、自分達で対策は可能なので、この記事でも紹介している方法を参考にしてみてください。
また、安全に早く状況の改善をしたい方は害獣駆除の専門業者へ相談する方法もあります。
ぜひ、自身にあった方法を検討してみてください。
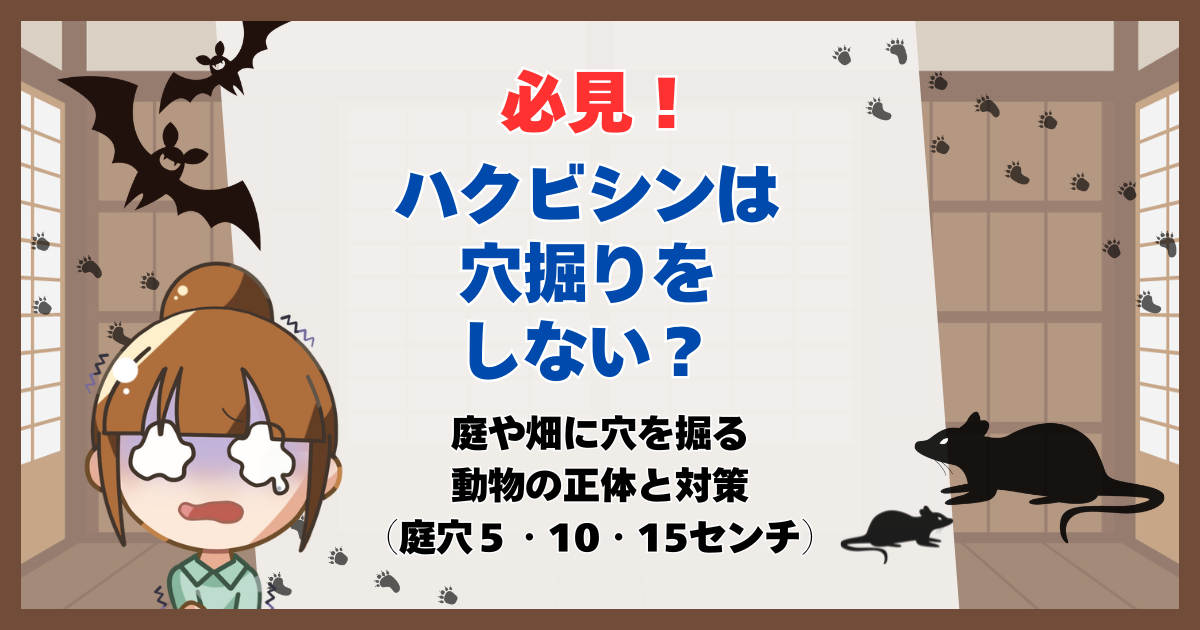





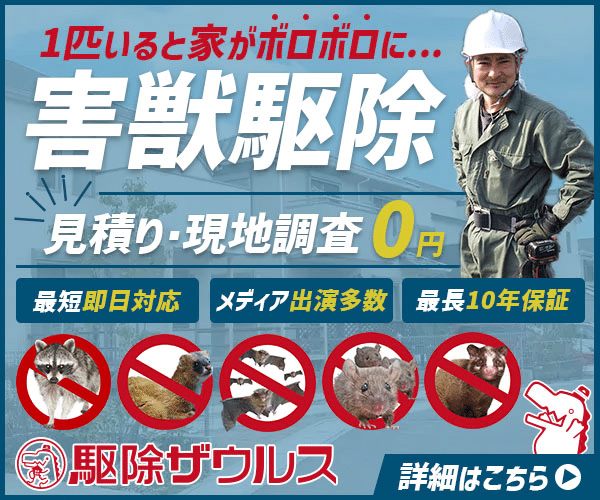






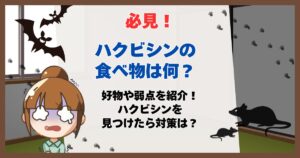
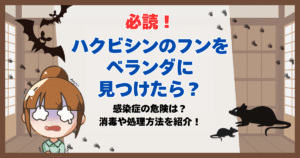
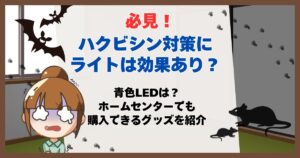



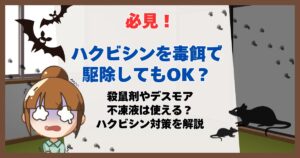
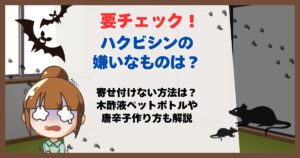
コメント